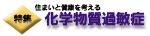|
然の反応だ。K君は有毒なものをいち早く体で教えてくれている。K君の体に悪いものはみんなにも悪いのだ。だからK君に悪いものを避けることは、みんなの健康にとっても、たいへん大切なことだ」というとらえ方でした。
けれども、すべての学校がN校のような対応をしてくれるとは限りません。N校にも以前は「1200人中の1人のために、そんなことはできないよ」と言った先生もいました。個人が学校に協力をお願いしても限界があります。相談を受けた先生次第で、取り合ってもらえないケースもあります。一方で化学物質過敏症の子どもの数はどんどん増えています。いま江別市内の小中学校では化学物質過敏症の子は数人ですが、幼稚園児となると一つの幼稚園に3人くらい。確実に増えています。
今年の4月、私が代表になって「子どもの健康と環境を守る会」を結成しました。できるだけ多くの人に化学物質過敏症について知ってもらい、学校という公共の場で化学物質過敏症の子をこれ以上増やさないでほしいと、講演会やミニ勉強会を開いたり、ビデオや資料の貸し出しも行っており、いまは夏休み中の学校の補修について江別市や教育委員会と話し合っています。学校や地域、社会を変えなければこの問題は解決しません。そのためには、まず化学物質過敏症についての知識をもってもらう、理解してくれる人を増やす、そして一人一人の意識を高めていくことが必要だと思います。
|