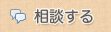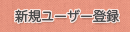築13年戸建てです。
基礎の一部ですが立ち上がり部に茶色の約1メートルくらいのシミを見つけたのが始まり(去年10月くらい)です。シミ周りの砂利や土が湿っていました。ベタ基礎です。表面はモルタル化粧しています。
シミがついた基礎の内部は浴槽(内断熱材あり)があります。
シミ周りの土に問題があると思い、まず土を掘り給水栓を閉めてメータ確認(3分)をしましたが給水による漏れはありませんでした。浴室にお湯をためて排水時に土の様子を確認しましたが特に漏れはなかったです。
更に気になる事があり、気温が低い時や雨時に基礎のシミ周りから基礎が濡れた様な状態(1.5メートルくらい)になります。(シミのある辺りの基礎が雨に当たる事はほとんどない)濡れた基礎部は立ち上がり部分で、その下側(床側)濡れていない。
ハウスメーカーの人は問題ないといいますが、、雨関係なしでも気温の変化で立ち上がり基礎が濡れたり乾いたりするのは大丈夫なのでしょうか?シミは気温が高くなると低い時よりは薄くなりますが消えません。
モルタル化粧とコンクリートの間に結露か水が溜まっているのか?と素人ながらに考えたりしています。また茶色いシミはブラシやヤスリでこすったりしても全く落ちません。このシミは錆等の可能性も考えています。
一度モルタル化粧を破壊してコンクリートを確認する事も検討しています。
いい案をいただければ有り難いです。
宜しくお願いします。

基礎の一部ですが立ち上がり部に茶色の約1メートルくらいのシミを見つけたのが始まり(去年10月くらい)です。シミ周りの砂利や土が湿っていました。ベタ基礎です。表面はモルタル化粧しています。
シミがついた基礎の内部は浴槽(内断熱材あり)があります。
シミ周りの土に問題があると思い、まず土を掘り給水栓を閉めてメータ確認(3分)をしましたが給水による漏れはありませんでした。浴室にお湯をためて排水時に土の様子を確認しましたが特に漏れはなかったです。
更に気になる事があり、気温が低い時や雨時に基礎のシミ周りから基礎が濡れた様な状態(1.5メートルくらい)になります。(シミのある辺りの基礎が雨に当たる事はほとんどない)濡れた基礎部は立ち上がり部分で、その下側(床側)濡れていない。
ハウスメーカーの人は問題ないといいますが、、雨関係なしでも気温の変化で立ち上がり基礎が濡れたり乾いたりするのは大丈夫なのでしょうか?シミは気温が高くなると低い時よりは薄くなりますが消えません。
モルタル化粧とコンクリートの間に結露か水が溜まっているのか?と素人ながらに考えたりしています。また茶色いシミはブラシやヤスリでこすったりしても全く落ちません。このシミは錆等の可能性も考えています。
一度モルタル化粧を破壊してコンクリートを確認する事も検討しています。
いい案をいただければ有り難いです。
宜しくお願いします。

タンクン
所在地:香川県
2025年03月17日 15:47
これまでの回答・ご意見数5件
アドバイザーからの回答
 アドバイザー
アドバイザー  相談者
相談者
※アドバイザー以外の一般ユーザーからのご意見
 一般ユーザー
一般ユーザー  相談者
相談者

取締られ役平社員
所在地:北海道
2025年03月18日 09:10
URL:
家づくりの想い:
>シミがついた基礎の内部は浴槽(内断熱材あり)があります。
>雨関係なしでも気温の変化で立ち上がり基礎が濡れたり乾いたりするのは大丈夫なのでしょうか?
あくまでも「複合的な要因」であろうと考え、そのうちの一つの要因。ということで・・・・お風呂は「ユニットバス」でしょうか?あるいは「造作風呂」と言われるものでしょうか?
いずれにしても、浴槽なり、浴室の壁なり、断熱の欠損があるのであろうと考えました。
たとえば、ユニットであっても通常のおさまりとして、浴槽部分は低く掘り下げてあることと思われますが、その掘り下げのために、壁断熱と、浴槽周辺の断熱との間に隙間が生じていたり、土台下と、基礎との間の隙間がそのままだったり。と、注意を払う必要のある部分が多い箇所です。
一時期、その掘り込み部分の断熱に「グラスウール」を「ネット」で囲い、吊っているおさまりがありました。この場合は、ネット内でグラスウールが下がり、周辺で隙間が空く事例がありました。
造作風呂であったとして、
同じく浴槽部分が掘り下げてあった場合、その浴槽周辺にはグラスウールということはできません。(グラスウールでも大丈夫なおさまりをしていない限り)板状の断熱材(スタイロフォームなど)になるでしょう。
時期によっては、最悪はそれすらもを入れていない場合も見受けられました。
無断熱である可能性もあり、「結露」を恐れる場合、考えられる要因ではあるわけです。
>一度モルタル化粧を破壊してコンクリートを確認する事も検討しています。
必ずしも、それが大きな要因を発見、対策に通じるとは私自身は考えません。
浴室の断熱を文字通り「重箱の隅をつつく」がごとく、点検することが必要ではないか?と考えます。

タンクン
所在地:香川県
2025年03月18日 21:52
返信ありがとうごさいます。
我が家は「ユニットバス」です。
取締まられ役平社員さんに言われて、床下断熱が気になり初めて自分で床下点検をしました。
ハウスメーカーの10年点検時には床下点検してもらい異常なしと言われて安心していました。
床下点検をして色々確認しましたが、まず浴室の基礎3面に断熱材があり、浴室床下コンクリート部にも断熱材が敷かれていました。
基礎3面の断熱材の上に壁断熱ボード?石膏ボードみたいなのが立ち上がっていました。断熱材と石膏ボードみたいなものとの当たり部には発泡ウレタン細く打っています。
浴室と隣の脱衣場の間には基礎も何もなく空間が繋がった状態なので浴室は気密ではないと判断出来ました。図面での確認ですが浴室の基礎パッキンは気密ではなく間隔を空けての通気用のパッキンが施工されている様です。
発泡ウレタンは断熱材と立ち上がり基礎の間に塗布されていない部分もあり、、床下コンクリート部の断熱材同士の繋ぎ部の隙間にも発泡ウレタンが出来ていなかったり、、施工は荒い感じだなっと感じました。
浴室が気密でない事もあり断熱材と基礎の間に結露が出来ているのかなって焦ったりします。断熱材は濡れてなかった様に思いますが、、。
一度断熱材を全て除去した方がいいのでしょうか?
最近家を建てた職場の若い子達の話によると今は完全気密(人通口あり)みたいで、約15年前とは違うのかなって思ったりしてます。
私の家の断熱施工は考えられないと言われたりしてます。
一度ハウスメーカーの浴室断熱施工に詳しい人に来てもらい、我が家の施工は間違いのない施工か点検してもらおうか考え中です。
我が家は「ユニットバス」です。
取締まられ役平社員さんに言われて、床下断熱が気になり初めて自分で床下点検をしました。
ハウスメーカーの10年点検時には床下点検してもらい異常なしと言われて安心していました。
床下点検をして色々確認しましたが、まず浴室の基礎3面に断熱材があり、浴室床下コンクリート部にも断熱材が敷かれていました。
基礎3面の断熱材の上に壁断熱ボード?石膏ボードみたいなのが立ち上がっていました。断熱材と石膏ボードみたいなものとの当たり部には発泡ウレタン細く打っています。
浴室と隣の脱衣場の間には基礎も何もなく空間が繋がった状態なので浴室は気密ではないと判断出来ました。図面での確認ですが浴室の基礎パッキンは気密ではなく間隔を空けての通気用のパッキンが施工されている様です。
発泡ウレタンは断熱材と立ち上がり基礎の間に塗布されていない部分もあり、、床下コンクリート部の断熱材同士の繋ぎ部の隙間にも発泡ウレタンが出来ていなかったり、、施工は荒い感じだなっと感じました。
浴室が気密でない事もあり断熱材と基礎の間に結露が出来ているのかなって焦ったりします。断熱材は濡れてなかった様に思いますが、、。
一度断熱材を全て除去した方がいいのでしょうか?
最近家を建てた職場の若い子達の話によると今は完全気密(人通口あり)みたいで、約15年前とは違うのかなって思ったりしてます。
私の家の断熱施工は考えられないと言われたりしてます。
一度ハウスメーカーの浴室断熱施工に詳しい人に来てもらい、我が家の施工は間違いのない施工か点検してもらおうか考え中です。

取締られ役平社員
所在地:北海道
2025年03月19日 09:27
URL:
家づくりの想い:
>まず浴室の基礎3面に断熱材があり、浴室床下コンクリート部にも断熱材が敷かれていました。
十数年前の新築であれば、当たり前か少し先進性の認められるおさまりではないか?と思われます。
>浴室と隣の脱衣場の間には基礎も何もなく空間が繋がった状態なので浴室は気密ではないと判断出来ました。
基礎が全周にあることが理想ですが、基礎が無い場合でも、断熱材、この場合は板状の断熱材を壁にして施工しておくことが必須となるでしょう。
要は、断熱材が隙間なく「箱」になっていることが第一歩です。
その後、断熱材の「厚さ」、気密の度合いが問題点になるでしょう。
>基礎3面の断熱材の上に壁断熱ボード?石膏ボードみたいなのが立ち上がっていました。断熱材と石膏ボードみたいなものとの当たり部には発泡ウレタン細く打っています。
写真では判断が難しいのですが、断熱材が切れ目なくつながり、その接続部で、十分な厚さを確保していることが、必要となるでしょう。
例えば、100mmでお互いに接続しているとして、接続面に50mmの段差があったとすると、実はその接触している部分では、100mmの厚さが確保されていません。50mmしかないのです。こういう段差になることが想定される場合は、単純に「つなぐ」のではなく、「重ねる」考えが必要ですよね?ご理解いただけますか?で、そのような目で確認されることをお勧めします。
>図面での確認ですが浴室の基礎パッキンは気密ではなく間隔を空けての通気用のパッキンが施工されている様です。
この場合、せっかくの「壁断熱」の厚みは基礎パッキンの部分は「0」です。
もちろん、隙間をそのままであれば、気密も「0」でしょうね。
壁の断熱と、基礎の断熱を重ねることが必要なのは、ご理解いただけますか?あるいは、浴室周りだけでも、気密パッキンは無し、あるいはウレタンなどでしっかり埋める必要があると考えられます。
>一度断熱材を全て除去した方がいいのでしょうか?
私としては、お勧めしません。
けがをしました。・・・全身を「裸」にしますか?
しません。・・・けがをした部分だけ「衣服を切る」とか「衣服を脱がせる」ことで対応します。
今回の場合も、「要所」の周辺の断熱材撤去、「点検・修繕」後に再度の断熱施工で必要充分と考えます。
「要所」の見定めに注意と経験が必要かと考えます。
「施工業者」や「責任のある第三者」の現場確認、助言をお願いしてみたらいかがでしょう?

タンクン
所在地:香川県
2025年03月19日 20:48
返信ありがとうごさいます。
取締まられ役平社員さんの説明のおかげである程度納得、理解ができました。
ほぼ無知の私でしたが今後のやるべき事が見えてきました。
今回の件でまず1番気になる所は屋外基礎部の茶色シミ、気温の変化による濡れがメインなのでそれの原因追求が出来れば納得、安心出来ますので。
おっしゃる通りハウスメーカーの「施工業者」に「要所」をしっかり伝えて確認して行きたいと思います。13〜14年前なので辞めていないかも知れませんが、、。
どっちにしても今回で得た知識で色々話してみます。
「責任ある第三者」も視野に入れて点検、対策もして行きたいと考えます。
色々とありがとうございました。
また縁があればその時は宜しくお願いします。
取締まられ役平社員さんの説明のおかげである程度納得、理解ができました。
ほぼ無知の私でしたが今後のやるべき事が見えてきました。
今回の件でまず1番気になる所は屋外基礎部の茶色シミ、気温の変化による濡れがメインなのでそれの原因追求が出来れば納得、安心出来ますので。
おっしゃる通りハウスメーカーの「施工業者」に「要所」をしっかり伝えて確認して行きたいと思います。13〜14年前なので辞めていないかも知れませんが、、。
どっちにしても今回で得た知識で色々話してみます。
「責任ある第三者」も視野に入れて点検、対策もして行きたいと考えます。
色々とありがとうございました。
また縁があればその時は宜しくお願いします。

現場監督A
所在地:神奈川県
2025年03月19日 21:47
URL:
家づくりの想い:現場監督歴20年。アフターも…
ちょっと別の視点で少し思ったことを記述させていただければと思います。床下内部での基礎コンクリートと基礎断熱材との隙間の結露→その結露水がコンクリート打ち継ぎ部から浸水→鉄筋が錆びて外部の茶色いシミになっている?、っていう疑念のお話かと思いますが、その可能性は極めて低いのかなと思います。あり得なくはないですが。ユニットバスですとそもそも漏水でもしていない限り床下に湿気が漏れることはほぼ無いですし、浴室と脱衣所に仕切りがないということですので、浴室以外のしっかり換気のされた床下空間と繋がっているわけで、湿度が上昇する様子が見当たりません。浴室に常に水が溜まっているような高湿潤の状態じゃない限り結露ってあるかな〜?って思います。
私の経験上、基礎立ち上がり部分が茶色くなるのは土壌中の水分の吸上げの可能性が一番高いと思います。色が変わっている形状としても吸い上げではないかと。サビ汁が出てきているのだとすると、鉄筋というよりもセパレーターの間隔でもっとはっきりと浮き出てくるはずです。基礎色を変えるほどの錆汁が出ている場床下にもその程度の水量かその乾いた跡が残っているはずです。
なので、基礎巾木の化粧モルタルが多少浮いてしまったことによって、土中の土や灰汁を含んだ水が基礎コンクリートと化粧モルタルの間にできた隙間に毛細管現象で吸い上がって基礎を茶色く変色させたって言うのが一番現実味のある現象です。
したがって、どうしても気になるようであれば、変色部分の化粧モルタルを一度剥がしてみると良いかもしれません。剥離具合次第では簡単にポロっと剥がれるかもしれません。
私の経験上、基礎立ち上がり部分が茶色くなるのは土壌中の水分の吸上げの可能性が一番高いと思います。色が変わっている形状としても吸い上げではないかと。サビ汁が出てきているのだとすると、鉄筋というよりもセパレーターの間隔でもっとはっきりと浮き出てくるはずです。基礎色を変えるほどの錆汁が出ている場床下にもその程度の水量かその乾いた跡が残っているはずです。
なので、基礎巾木の化粧モルタルが多少浮いてしまったことによって、土中の土や灰汁を含んだ水が基礎コンクリートと化粧モルタルの間にできた隙間に毛細管現象で吸い上がって基礎を茶色く変色させたって言うのが一番現実味のある現象です。
したがって、どうしても気になるようであれば、変色部分の化粧モルタルを一度剥がしてみると良いかもしれません。剥離具合次第では簡単にポロっと剥がれるかもしれません。

現場監督A
所在地:神奈川県
2025年03月19日 21:53
URL:
家づくりの想い:現場監督歴20年。アフターも…
あ、化粧モルタルを剥がす前に簡単に確認できることしたら、2枚目のお写真のように土を掘り上げた状態で様子を見ることですかね。この状態なら土中の水分が吸い上げる事がありません。これで薄いままであれば埋め戻しを透水性の高い砂利などですれば解決するかもしれません。化粧モルタル納期が大きければ軽くコツコツ叩くと軽い音がするかもしれません。


タンクン
所在地:香川県
2025年03月20日 08:07
返信ありがとうごさいます。
現場監督Aさんの錆汁の可能性が低いと言うお言葉で少し安心出来ました。
モルタル化粧の一部破壊を検討してますが、最初に床下の浴槽断熱の施工を見直す計画中です。
因みに写真2.3は気温が低い時(曇りや雨)の写真で4.5は気温が高い時(晴れ)の写真です。
どちらも土を掘り下げた状態での写真になります。(掘り下げた状態で観察していました)
ですので、土の吸い上げ関係なしで気温によってモルタル化粧の濡れ、乾きが発生している状態だと思います。茶色部分も気温が低いと色濃くなりますし、、。
ここの部分はほとんど雨も当たらない場所なので濡れ状態が凄く気になっています。
現場監督Aさんの錆汁の可能性が低いと言うお言葉で少し安心出来ました。
モルタル化粧の一部破壊を検討してますが、最初に床下の浴槽断熱の施工を見直す計画中です。
因みに写真2.3は気温が低い時(曇りや雨)の写真で4.5は気温が高い時(晴れ)の写真です。
どちらも土を掘り下げた状態での写真になります。(掘り下げた状態で観察していました)
ですので、土の吸い上げ関係なしで気温によってモルタル化粧の濡れ、乾きが発生している状態だと思います。茶色部分も気温が低いと色濃くなりますし、、。
ここの部分はほとんど雨も当たらない場所なので濡れ状態が凄く気になっています。

現場監督A
所在地:神奈川県
2025年03月27日 23:39
URL:
家づくりの想い:現場監督歴20年。アフターも…
返信いただいていたのに気が付かなくてすみません。
掘り起こした状態で様子を見ているんですね。お写真の状況で少し気になる点としては、3、5枚目の写真を見ると一部掘り返していない部分がありますね。何らかの自由で土中が湿潤状態になった場合、この部分から吸い上げることもありうるのかなと想像しました。もちろんそういった場合は掘り返した部分も土が湿ったりすると思いますので、それがないと可能性は低いかもしれませんね。
1枚目の掘り返す前のお写真と思いますが、かなり茶色く土や砂利が変色しておりますよね。これが内部からの結露水だけでこんなに水量が出てくるかな?って言う疑念があります。なので中からじゃなくて外の問題なんじゃないかなと思います。
そういった目線であらためて全お写真を見ると、可能性は低いですが、3枚目のお写真の茶色い縦樋の脇に給水管が立ち上がってキャップ止めしてありますね。これは何なんでしょうかね。その左側に立水栓らしきものがあります。この辺の老衰をもう一度再確認する価値はありそうです。
結露の路線の方で、「気温」が高い低い時という表現をされておりますが、床下の結露を疑うようであれば、床下の湿度と、床下基礎表面温度を定期的に記録をとると良いと思います。基礎と断熱の間の結露だと湿度は参考にならないかもしれませんが、表面温度によって、結露する水蒸気量が現実味があるかないかを判断できます。
掘り起こした状態で様子を見ているんですね。お写真の状況で少し気になる点としては、3、5枚目の写真を見ると一部掘り返していない部分がありますね。何らかの自由で土中が湿潤状態になった場合、この部分から吸い上げることもありうるのかなと想像しました。もちろんそういった場合は掘り返した部分も土が湿ったりすると思いますので、それがないと可能性は低いかもしれませんね。
1枚目の掘り返す前のお写真と思いますが、かなり茶色く土や砂利が変色しておりますよね。これが内部からの結露水だけでこんなに水量が出てくるかな?って言う疑念があります。なので中からじゃなくて外の問題なんじゃないかなと思います。
そういった目線であらためて全お写真を見ると、可能性は低いですが、3枚目のお写真の茶色い縦樋の脇に給水管が立ち上がってキャップ止めしてありますね。これは何なんでしょうかね。その左側に立水栓らしきものがあります。この辺の老衰をもう一度再確認する価値はありそうです。
結露の路線の方で、「気温」が高い低い時という表現をされておりますが、床下の結露を疑うようであれば、床下の湿度と、床下基礎表面温度を定期的に記録をとると良いと思います。基礎と断熱の間の結露だと湿度は参考にならないかもしれませんが、表面温度によって、結露する水蒸気量が現実味があるかないかを判断できます。